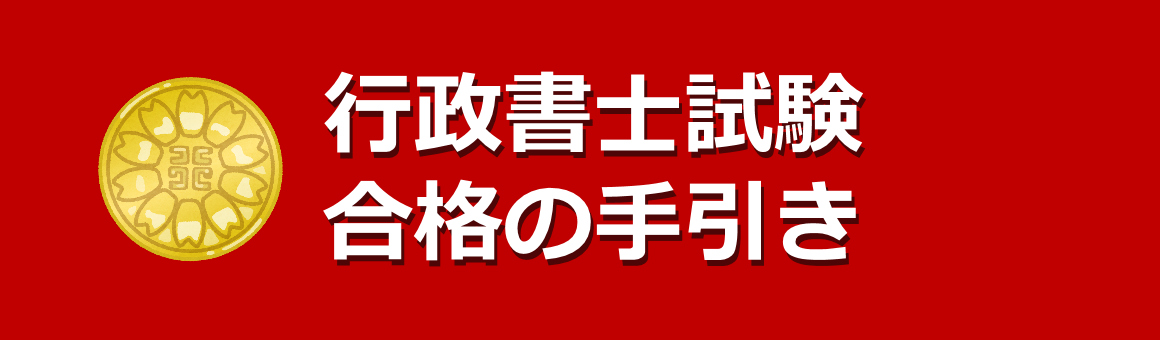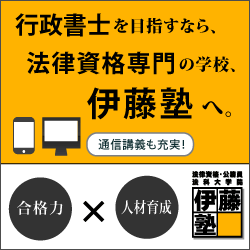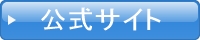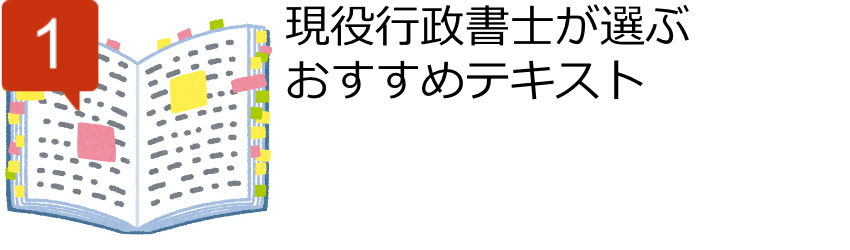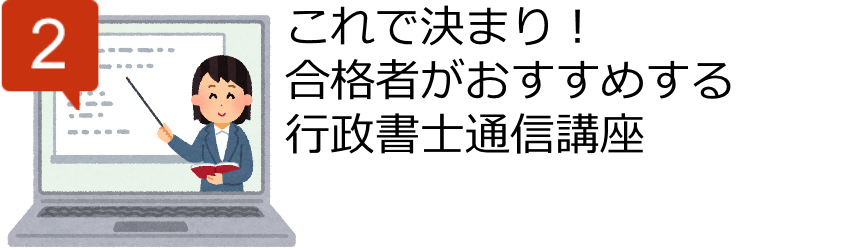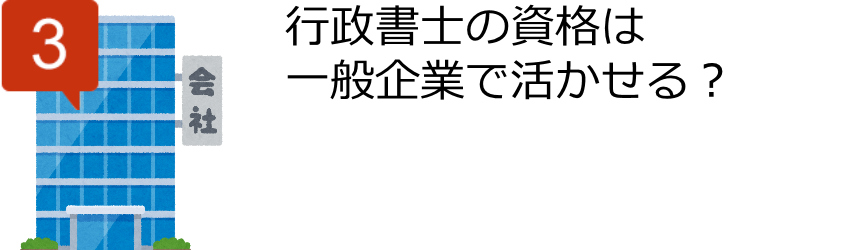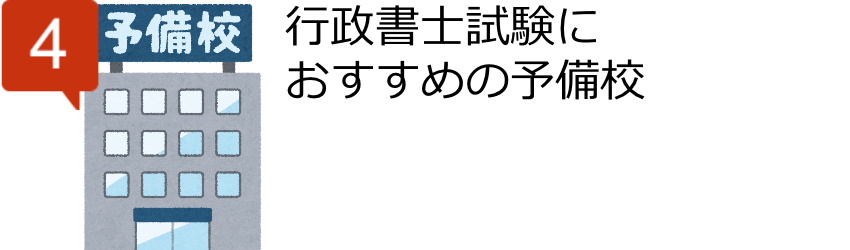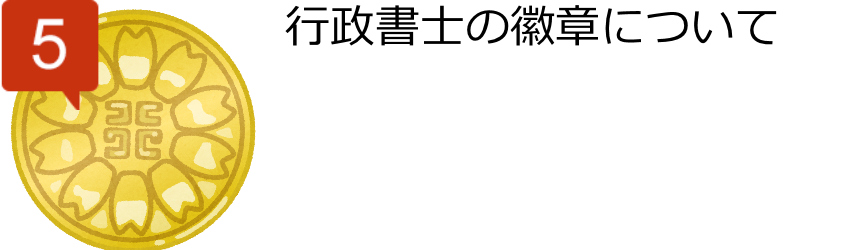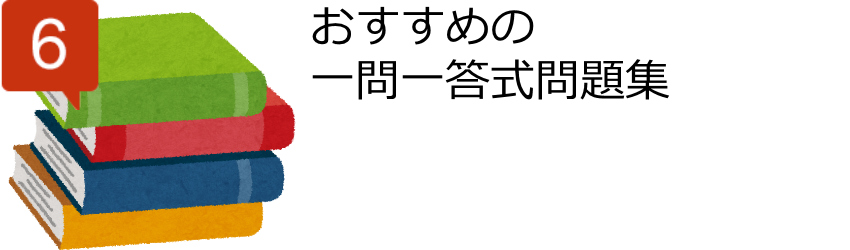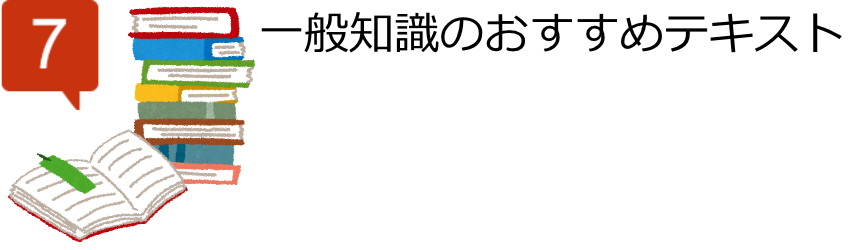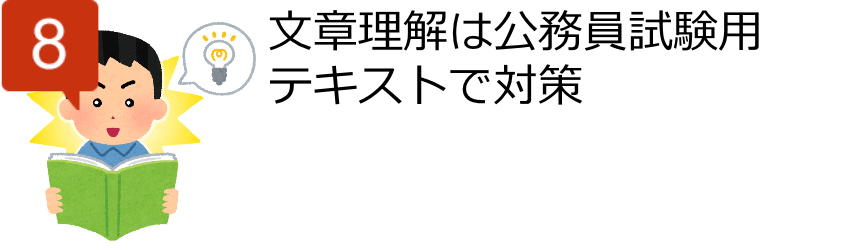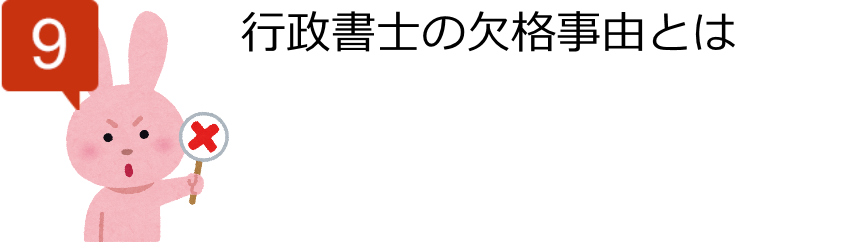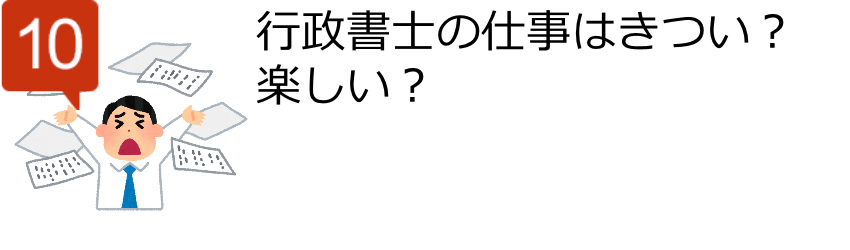行政書士試験の一般知識の科目と出題傾向について解説していきます。
行政書士試験の一般知識には足切りが存在するのでしっかりとした対策が必要です。
科目と出題傾向を把握し、攻略していきましょう。
一般知識の科目
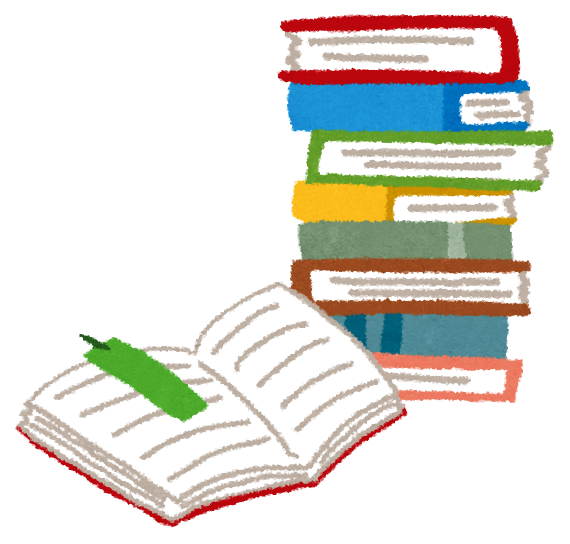
- 政治・経済・社会
- 情報通信・個人情報保護
- 文章理解
行政書士試験の一般知識は上記の3つが科目となります。
政治・経済・社会
政治・経済・社会の問題数は7〜8問。
とても幅広い知識を問われるのが政治・経済・社会です。
政治では主に国会や政党などの政治制度、自治体や地方公共団体の行政に関する問題が出題されます。
日本だけでなく世界の政治制度も問われるので、各国の政治の特徴も押さえておく必要があります。
また歴史や地理に関する問題も出題されます。
経済は日本の金融政策、貿易、公正取引委員会や独占禁止法などの様々な問題が出題されます。
そこまで難問は出題されず基本的なことが問われます。
また時事問題も絡ませて出題してくる傾向があります。
社会は社会問題となっている事柄や社会制度、環境問題などが出題されています。
時事問題から年金・税金に関する問題など、とにかく出題範囲が広いです。
小説に関する問題が出題されるなど一見、行政書士とは関係ない分野からも出題されます。そのため単純に知っていれば解けるが知らなければ解けないという風に、知識の多さが得点の鍵を握っています。
情報通信・個人情報保護
情報通信・個人情報保護の問題数は3〜4問。
情報通信では主にインターネット技術に関する問題が出題されます。
通信技術の基本的な知識から、行政手続き、電子署名、e-文書などについての知識が問われます。
インターネットについての用語をそのまま問う問題や、特定商取引法や消費者契約法などと知識を絡めた法令問題も出題されます。
個人情報保護は、個人情報保護法を中心に行政機関個人情報保護法や公文書管理法、情報公開法などが問われます。
主に条文からの出題となるので重要な条文はしっかりと把握しておく必要があります。
また、複数の法律を複合的に問う問題も出題されます。
比較的、勉強すれば得点しやすい科目でもあります。
文章理解
文章理解の問題数は3問。
文章理解は用意された長文に対して、並べ替え問題や空欄補充問題、要旨把握問題といった形式で出題されます。
得意不得意がはっきり分かれる科目です。
国語が得意な人や読書が好きな人は勉強せずとも得点できてしまいますが、不得意な人にとっては鬼門となる科目です。
解法テクニックを身につければ得点しやすい科目ですので、是非とも3問正解を目指したいところです。
【平成30年度】一般知識の出題傾向
- 外国人技能実習制度
- 資格事務をつかさどる省庁について
- 消費生活協同組合について
- 日本の貿易および対外直接投資
- 墓地および死体の取扱い等について
- 地方自治体の住民等について
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律について
- 防犯カメラの設置について
- 欧州データ保護規則について
- 個人情報の保護に関する法律について
- 経済 ⇒ 1問
- 社会 ⇒ 5問
- 個人情報保護 ⇒ 3問
- その他 ⇒ 2問
平成30年度の一般知識は外国人技能実習制度や墓地、風営法など行政書士業務に密接な問題が多く出題されました。
行政書士試験は実務とかけ離れているとよく言われるので、個人的にはこういった問題が増えることは良いことだと思います。
また、最近の出題傾向としては時事問題が多く出題されていることが特徴としてあります。
【平成29年度】一般知識の出題傾向
- 各国の政治指導者に関して
- 公的年金制度について
- 農業政策について
- ビットコイン
- 度量衡
- 消費者問題・消費者保護について
- 小説家・山崎豊子の著作
- クラウド
- 著作権
- 情報技術
- 情報公開法制と個人情報保護法制
- 政治 ⇒ 2問
- 経済 ⇒ 1問
- 社会 ⇒ 4問
- 情報通信 ⇒ 2問
- 個人情報保護 ⇒ 1問
- その他 ⇒ 1問
平成29年度の試験においてもビットコイン(仮想通貨)や各国の指導者に関する問題など今まさに話題となっている内容が出題されています。
また経済×情報通信といったように他の科目と絡めた複合的な問題も出題されました。
一部の科目だけの知識ではなく、総合的な学習が必要となるでしょう。
最近、法改正された分野からも出題されています。
基本的な知識を得ておくことはもちろんのこと、その知識のアップデートも必要となります。
度量衡に関する問題も出題され、行政書士の実務でも使えそうな知識が問われました。
度量衡とは測定、単位のこと。
長さ(=度)と容積(=量)と重さ(=衡)。
「各国の政治指導者について」
アメリカの大統領が新しく就任したこともあり、アメリカや北朝鮮といった各国の政治指導者の関する問題が出題されました。
「年金制度について」
年金の受給資格に関する法令の改正に伴い、年金制度についての出題がありました。
「農業について」
国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部改正、農協法の改正、農業競争力強化支援法の施行などから農業に関する問題が出題されました。
「ビットコインについて」
平成29年に話題となったビットコインに関する設問がありました。
「消費者問題」
不当景品類及び不当表示防止法における課徴金制度が運用されるようになったことから消費者問題と消費者保護に関する問題が出題されました。
・「クラウドについて」
クラウドソーシングとクラウドファンディングの「群衆」の意味のCrowdと、クラウドコンピューティングとしてデータの保存先としてのCloudの意味が問われました。
【平成28年度】一般知識の出題傾向
- 日本と核兵器の関係
- 改正公職選挙法
- 日本の中央政府の庁について
- TPP
- 日本の戦後復興期の経済
- 日本社会の多様化について
- 日本で発生した自然災害
- 人工知能
- IoT(Internet of Things)
- 情報処理
- 公文書管理法(公文書等の管理に関する法律)
- 政治 ⇒ 3問
- 経済 ⇒ 2問
- 社会 ⇒ 2問
- 情報通信 ⇒ 3問
- その他 ⇒ 1問
平成28年度の一般知識でもトピックや時事問題、改正法令を中心に出題されています。
「日本と核兵器について」
オバマ大統領が広島訪問したこともあり、日本と核兵器についての問題が出題されました。
「TPP」
2016年2月に署名されたTPP(Trans-Pacific Partnership)協定から出題。
「人工知能(AI)・IoT(Internet of Things)」
近年、話題となった人工知能やIoT(Internet of Things)からの出題。
「公職選挙法」
改正が行われた公職選挙法についての設問もありました。
近年の情報通信・個人情報保護の出題傾向について
以前の一般知識攻略としては情報通信・個人情報保護(3問程度)と文章理解(3問)で足きりを回避するという方法が主流でした。
情報通信・個人情報保護は比較的、勉強しやすく文章理解も得点しやすいと言われているからです。
しかし個人情報保護に関しては勉強しやすいという特徴がありますが、情報通信に関しては範囲も広く専門用語もあるので得意不得意がある科目と思われます。
そして近年では勉強しやすい個人情報保護より、勉強しにくい情報通信から多く出題される傾向があります(平成30年度は個人情報保護から3問出題されました)。
その為、単純に情報通信・個人情報保護と文章理解で足きりを回避できるという対策は通じなくなってくる可能性があります。
【近年の情報通信・個人情報保護の出題傾向】
平成30年度
個人情報保護…3問
平成29年度
情報通信…2問
個人情報保護…1問
公文書管理法…1問
平成28年度
情報通信…3問
著作権法…1問
平成27年度
情報通信…2問
情報公開法及び公文書管理法…1問
行政機関個人情報保護法…1問
平成26年度
情報通信…2問
個人情報保護…1問
平成25年度
情報通信…1問
個人情報保護…2問
情報通信・個人情報保護と文章理解だけで足切り回避を狙うのではなく、政治・経済・社会でも2〜3問は正解できるようにしていくのが理想です。
政治・経済・社会は範囲が恐ろしく広いので、時事問題を中心に学習していくことをおすすめします。
ツイート