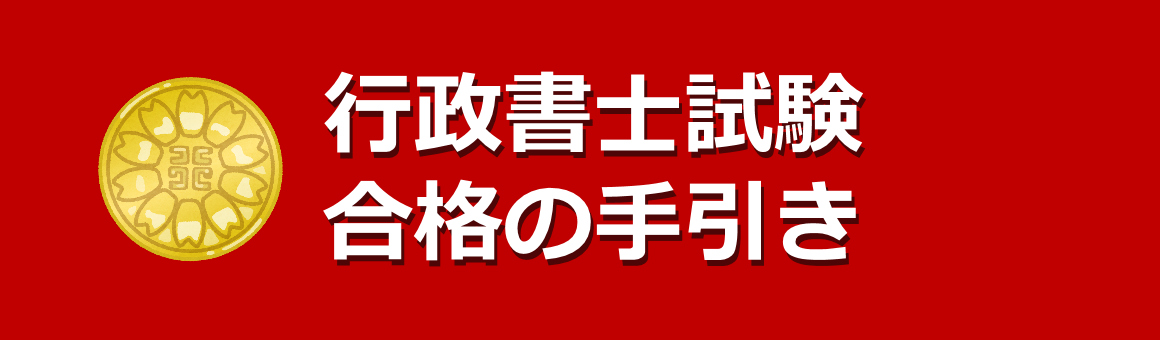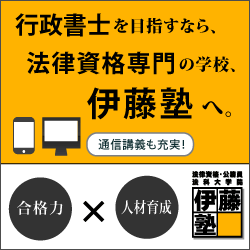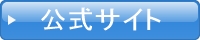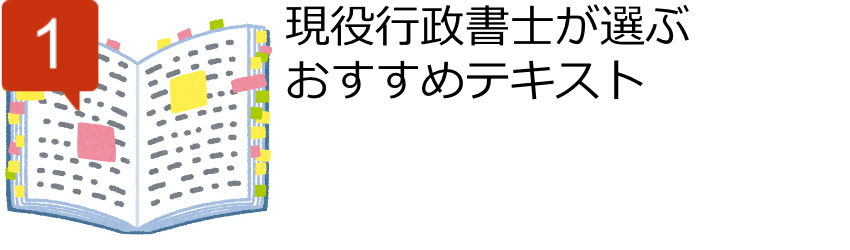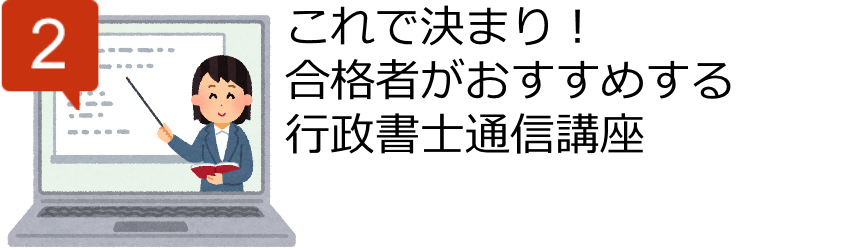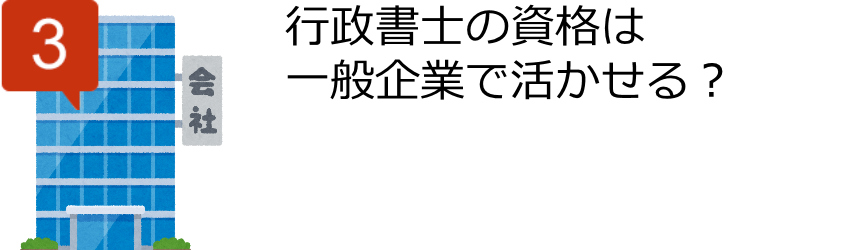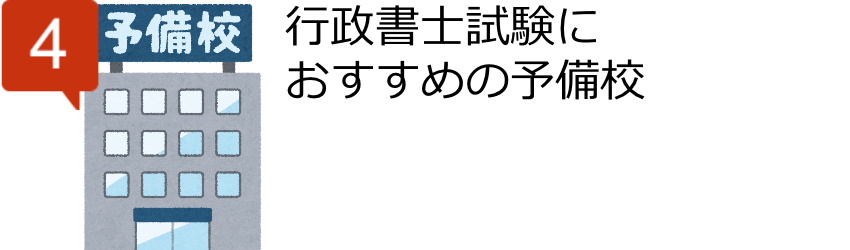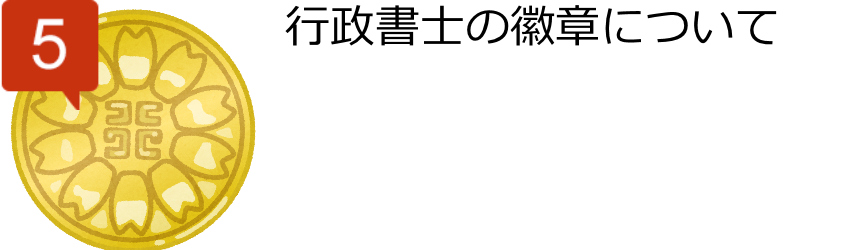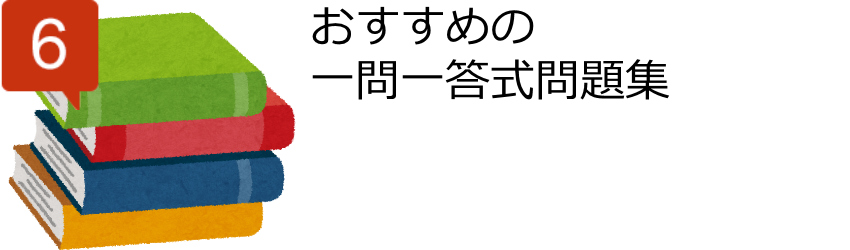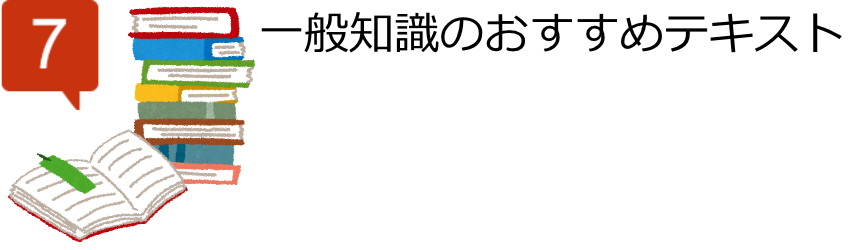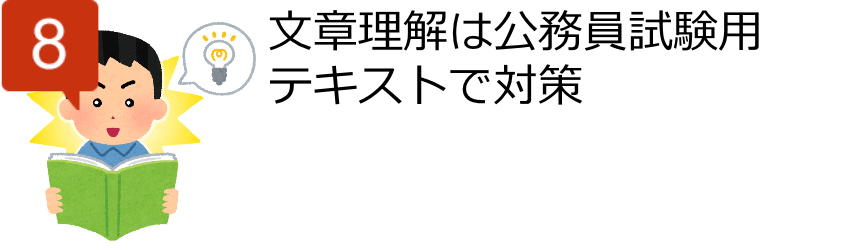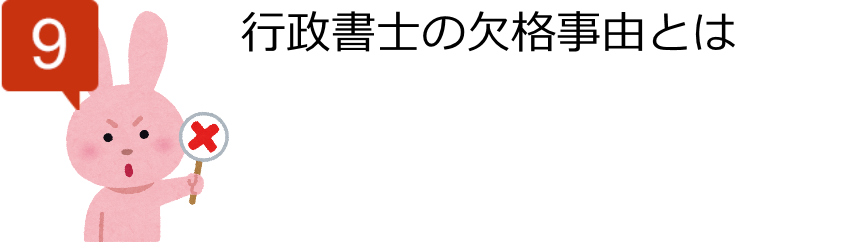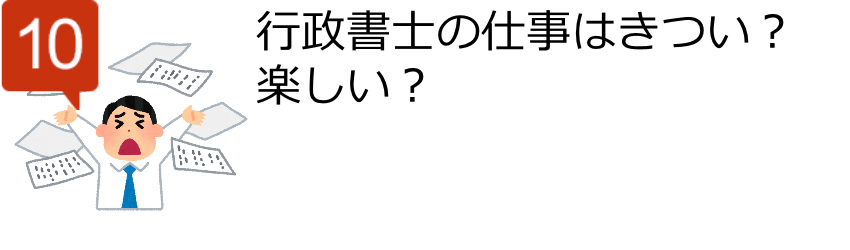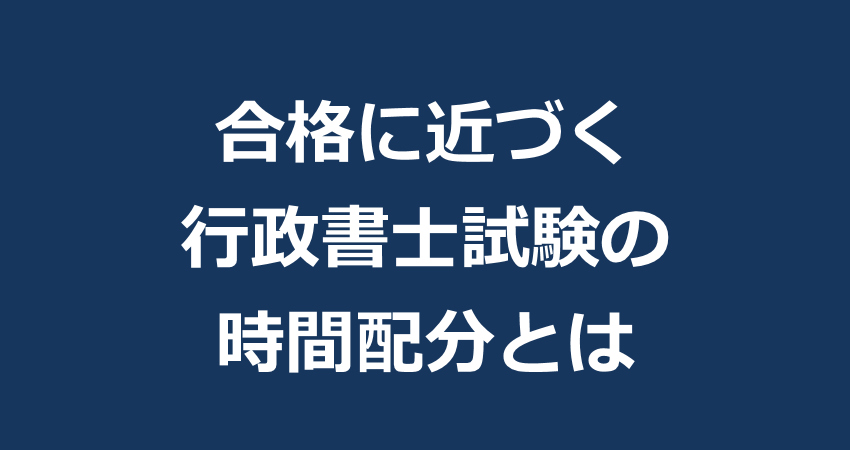
行政書士試験を乗り切るためには時間配分が必要です。
そこで今回は行政書士試験の時間配分について解説していきます。
長いようで短い試験時間
行政書士試験は13:00〜16:00までの3時間です。
なかなか3時間ぶっ通しの試験を経験されたという人は少ないと思いますが、行政書士試験は長いように見えて実はあっという間です。
行政書士試験は60問出題されますので1問あたり3分で解かなければなりません。
見直しやマークするなど時間を考慮すると2分半ほどになります。
受験経験のある人や模試を受験した人はわかると思いますが、結構きついです。
そのため、早く問題を解く必要があります。
ここを意識しないと「全部解けなかった」なんてことになります。
時間配分はすべきか
上記のように行政書士試験はあっという間に終わってしまいますので、早く解く必要があります。
なら早く解けば良いだけで、特に時間配分は必要ないのでは?と思う人もいるでしょうが、ある程度の時間配分は必要でしょう。
順調に解けているのか、それともペースを上げなければならないのか、基準となるものが必要だからです。
いつも通りのペースで解いているつもりでも、試験の難易度やその日の調子によって遅れている場合もあります。
時間配分をしていないと、それに気づくことができません。
ペースが遅れているのならば、ピッチを上げるか、優先順位の低い問題は後回しにするなど対策が必要となります。
時間配分の方法
一つの例として、私が実践した時間配分の方法をご紹介します。
私はあまり細かく決めずにざっくりと時間配分を決めました。
見直しの時間に10分、マークする時間を10分ほどは確保したかったので、実際に試験を解く時間は160分でした。
単純に計算すると、試験問題の30問目を解くのは試験開始80分後頃となります。
試験開始80分後というと、14:20です。
つまり14:20に30問目というのがひとつの目安となります。
14:20に30問目までいっていなければペースを上げる必要があるということになります。
実際には14:20前に何度か進捗状況を確認しておくことをおすすめします。
14:20に初めて確認したからまだ20問しか解いていなかった、なんてことになると取り戻すのが大変です。
最低でも14:00頃に一度は進捗状況を確認しておきましょう。
| 13:00 | 試験開始 |
|---|---|
| 14:00 | 進捗状況を確認 |
| 14:20 | 試験問題30問目に到達 |
| 15:40 | 全問終了(マークと見直し開始) |
| 16:00 | 試験終了 |
模試を活用して時間配分を決めよう
試験の解き方や解く順番など人によって違います。
なので、模試を活用して自分なりに時間配分を模索してみてください。
模試は実力を測ることもできますし、その年の試験傾向を知るメリットもありますが、何より本試験の予行練習をすることができます。
本試験では試験の攻略として解き方や解く順番、時間配分が大切になってきます。
これは人それぞれ方法が違うので、自分なり色々と試してみてください。
なので最低でも3回は模試を受験することをおすすめします。
| 1回目 | 問題点を見つける |
|---|---|
| 2回目 | 改善し、さらに問題点を見つける |
| 3回目 | 到達最終調整 |
ツイート